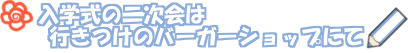
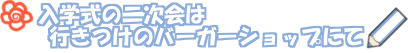
|
「それでは、今日はお疲れ様でした。明日の朝、また会いましょう」 そう言って、新たに私の担任となった深上葉湖(ふかがみ ようこ)先生は、にっこり微笑みバイバイと軽やかに手を振った。 はぁ……やっと終わった。 安堵した私は、誰にも気付かれないように、こっそりと溜息を吐いた。 久しぶりの登校。しかも、これまでみたいに私服ではなく初めて制服で登校するとあって、私らしくもなく緊張していた時間。その中学校入学の全プログラムが、先生の今の合図でようやく終了したのだ。 集団行動を好まない私は流石にもう息苦しくなってきていて、早々に違う空気の場所へと移動したかった。 配布された教科書と参考書を一冊一冊確認しながら、しかし素早く、学校指定の鞄と、それとは別に持ってくるように指示されていた予備の鞄の中に整理していく。学校指定の鞄だけでは容量が足りないのだ。 それほどまでに教科書類の冊数は多く、鞄が相当重くなるのは容易に想像できた。 これを持って帰らないといけないんだよなぁ。どうしよう、タクシーでも呼ぶか? ……いや、止めとこう。初日から変な注目を浴びるのは、逆に面倒だ。まぁ、式終了後も親が待っているところは車で帰宅するはずだから、そこまで目立ったりはしないのだけど……。 私の両親は、私が前もって来ないでくれと頼んでいたのでいるはずがない。 父親は仕事の鬼だからそっち優先だし、母親は母親であまり表に出るのが好きではない性格だから、「学校から帰ってきたら、おばあちゃんに送る写真を一枚だけ撮らせてね」とだけ言っていた。 周りから見れば自分勝手な親だと思われそうだが、私からすれば、こんなにも好都合な親はいない。 子供の私に無関心という訳でもないだろうが、良い意味で放任主義的な家庭で私は育った。 まぁ3人も子供がいれば、そうそう全員にも手を掛けてはいられないんだろう。 ちなみに私はその末っ子である。 大方の荷物を入れ終えた私は、最後に国語の教科書を手に取り、予備鞄の空いたスペースへと放り込んだ。そして、しっかり鞄の口を閉めると、僅かに目線だけを動かし教室を見渡してみる。 ふぅん、意外に静かね。 小学校から一緒のクラスだった人はともかく、大抵は初対面だったり初めて同じクラスになる生徒同士だったので、こういった場面でのガヤガヤッとした雰囲気は見られない。皆、そそくさと帰宅の準備をしていた。 もうすでに、3分の1くらいの生徒は見当たらない。 みんなも早く帰りたいのね。 特に男子生徒なんかは、先生の話を聞きながら、さして冊数の確認もせずにどんどん鞄を一杯にしていっていた。 だから、後々、教科書が一冊足りないとか言いだすヤツが出てくるのよね。まぁ私には関係ないけど。 しかし、多少なりとも関係のあるその人・深上先生は、相変わらずにこやかに教壇に突っ立っていて、そういう事態に陥りそうな生徒に注意を喚起することはなかった。 ただ、順々に教室を出て行こうとする新たな教え子達に、 「さようなら」 などと、呑気に挨拶している。 そういえば先生、自己紹介の時、25歳とか言ってたな。 若い先生だから、まだそこまで気が回らないのだろうか……。それとも、そんなことは個人の責任だ、ときっちり割り切っているのか? たぶん前者の方だろうけど、ただ面倒なだけ、とかいう安直な人間でないことは祈るしかほかない。 先生の外見はというと、まあまあ綺麗な先生だった。身長はけっこう高目で、フォーマルな薄いグレイのスカートスーツが良く似合っている。うっすらと赤みがかった髪を鮮やかな赤いバレッタでアップにきめていて、なかなかカッコイイ。 入学式だから、それなりの正装をしているのだろう。 だからって、教師としてきちんと仕事ができるのかは、まだ判らないけどね。 さてと、私もそろそろ帰らないと。 そう思った私は、冷たい椅子の淵に手を掛けた。 そして、そのまま素直に立ち上が……れば良かったのだけれど、一瞬早く、右後ろの席でガタッと椅子の鳴る音が聞こえてきた為、様子を見ることにした。 別に、私が立ち上がったからって問題が起こる訳じゃない。でも、これから通ろうとする人の通路を、私がわざわざ邪魔しなくてもいいだろう。 さぁ、道は空けといたわよ。さっさと行きなさい。 私は、ほとんど振り返ったとは言えないくらい小さく首を回して、目線を目一杯、右にずらす。 案の定、私の右後ろの席に座っていた女子生徒は、すくっと立ち上がって重そうな鞄の持ち手をつかんで抱き上げると、私のすぐ右横を通過して前の席の方へと歩いていった。 顔はよく見えなかったが、後姿を見る限り直毛のスッキリしたショートカット。身長は155㎝ある私と同じくらいで、同年代の女子と比べて背は高い。引き締まった筋肉を持ったふくらはぎが、制服のスカートから2本、すらりと生えていた。何かスポーツでもやってるのだろう。 どう見ても、私と友達になるような女の子でないのは確かだ。 そして彼女は、最前列の一番廊下側の席まで行くと足を止めた。 ああ、そうか。 やはりそこの席には、また別の女子生徒が座っていた。 仲の良い友達と一緒のクラスになったのね。 座っているその女子生徒は、あくせくした感じで、一所懸命に教科書類の整理をしている。 今度こそ、本当に帰ろう。 私は、椅子をゆっくりとずらして立ち上がった。 |
|
私には、こうして教科書を鞄に詰め込んでいる間に決心しなくてはならない事があり、そのことで朝から……いや、昨日の晩からずっと思い悩んでいた。 さぁ、どうする、咲真恭子……。 別に今日でなければならない、という訳でもないんだよな。帰ってから良く考えて、それから決めてもいいのかも知れない。ほとんどの生徒とは初対面なんだし、じっくり選んで……。 いや、しかしそれだと結局なあなあになって、先に先にと延ばしてしまいかねない。最初が肝心という事もあるし、それに、選ぶというのも相手に対して失礼だろう。ここは思い切って……。 それは、今日何度目かの自問自答だった。いくら繰り返しても、ハッキリとした答えなんて出るはずもないのに。 私の目的とは、恥ずかしながら友達をつくる、という事だった。 私は小学生の時に友達がいなかった、という訳ではない。でもそれは、前日のドラマの内容とかを楽しくおしゃべりしたりするような親友みたいな存在ではなく、言うなればライバル。つい先日まで私が所属していた陸上クラブで、必死になってタイムを競い合ってた人達だ。 学校で顔を合わせても、会話のほとんどが陸上に関しての内容。当時はそれでも、別に楽しくなかった訳でもないが、私の将来を考えた時、陸上に対しての情熱みたいなものがどうしても湧いてこなかったのだった。 そして私は、小学校を卒業した次の日に、そのクラブを辞めた。 当然、私をほぼ強制的にクラブに入れ、プロを目指す陸上選手を相手に仕事としてコーチをしている父は、反対した。 が、勘当されるくらいの覚悟で、断固として自分の意志を押し通すつもりだった私が、「勉強に力を入れる為に……」と嘘を吐くと、父は意外にもあっさり許してくれた。 父の言葉は「そうか、分かった」の一言だけだったが、私が初めて父に意見をした瞬間でもあり、それが通ったことが嬉しかった。 と同時に、本当はタイムなんかとは関係のない普通の女の子として生活したかったというだけの、ただの私のわがままを、嘘を吐いてまで押し通してしまったことに申し訳なさも感じていた。 こんな曖昧な気持ちで、友達なんてできるんだろうか。 もしかしたら、あの嘘を最後に、私の人とのつながりは途絶えてしまったのではないのか……。 そんな思いも頭の中をよぎって、私の決断を鈍らせる要因となっていた。 はぁ……。今日はもう、気分じゃなくなってきたなぁ。初日から友達をつくろうなんて、甘い考えを持っていた私が悪いんだ。 両親に、クラブを辞めて部活動もやらない代わりに、テストの成績を上位に維持すると約束したんだから、当分は学業優先。いずれ、友達ができるのを待つしかないんだ。 私は、ぐだぐだと悩む自分が段々嫌になってきていた。 さっさと家に帰って、教科書の裏に名前でも書こう。どうせ、誰に話し掛けたいのかも、全く決めてないんだから。 今日入学してきて、初めて知らされた新しいクラスメートに、小学校の時に同じクラスだった人はいない。私が唯一、気軽に話し掛けることができた女の子も、やっぱり同じ陸上クラブに同席していて、強豪の陸上部がある別の中学校に入学していってしまったのだ。 はぁ……。彼女はあっちの中学校でも上手くやっていけるんだろうなぁ。私と違って社交的な性格だったし。 ……ん? ふと気付くと、机の上に山積みにされていたはずの教科書と参考書は跡形もなくなっている。少し乱雑ながらも、全てが鞄の中に収まっていた。 知らないうちに、タイムリミットは来てしまっていたようだ。 やだ私ったら。いっつもなのよね。考え事をしてても、体は別の事でちゃんと働かせてるんだから。 仕方がないので、私はそのまま鞄のチャックを閉じる。チャックは教科書の角に突っかかったりして固くなっていたが、何度か強引に引っ張るとなんとかなった。 閉じる最後の瞬間に見えた鞄の中では、何かの教科書の表紙が変な方向に曲がってたような気がするが……。 まぁいっか、帰ろう。 私は立ち上がって、風船のようにバンバンに膨らんでいる鞄を持ち上げた。 ちょっと重いけど、これくらいなら問題ないわね。さて、どっちから出よう……。 私の席は後ろから2番目だから、距離としては後ろの出口を使った方が近んだけど、一応、一言くらい先生に挨拶していった方が良いかな。 そう思った私は、最短距離を無視して、まだ何人か座っている机の間を通って教室の前の方に歩いて行った。 その私に背を向けている新しいクラスメート達は、まだゆっくり教科書の整理をしていたり、何か考え事の最中なのか、ただボーっと座っていたりと千差万別で、だがこれといって特に気にするような生徒はいなかった。 しかし。 ん? あの子、何してんだ? しかし、そんな中において、一番前の席で1人だけ奇妙な事をしている女子生徒の席の横で、私はついつい足を止めてしまった。 後ろから見ただけでは気付かなかったが、その女の子は、せっかく鞄の中に入れた教科書を何冊か出しては別の教科書を入れたり、また出しては入れたりを繰り返していたのだ。まるで泥棒か何かが、沢山ある鍵束の中から鍵穴に合うものを一つ一つ探していってるような、少し焦りのある妙に怪しい動き。 何をしてるのか見当もつかないけど、そういえば見た事のある顔だなぁ。 私はその横顔に、かろうじて見覚えがあった。 え~と……多分、小学校が同じだった女の子だ。もちろん、同じクラスにはなった事がないけど。名前はたしか……。 自己紹介の時の記憶を思い起こす。なんとも申し訳ないが、同じ小学校だからといって全員の名前を覚えている訳ではなく、せいぜい半分くらい。ハッキリ言って先日までは、そんなヒマがないくらいに、頭の中は陸上競技一辺倒だったのだ。 ……たしか、浅木沙那(あさき さな)さん、だったよな。 顔は知っていたものの、会話などした事のないただの同級生だ。 「…………」 私は好奇心からか、そのほとんど初対面のような相手のすぐ真横で、無意識のうちに直立不動になっていた。 その私に気付いた彼女が、「ん?」というような表情でこちらに振り向いて、そして……。 目が合った。 |
|
がひょ~ん……ううぅ、これもダメだったよ。 どうにかしてどうにかすると、きちんと入りそうな感じはするんだけどなぁ。 ほとんどの参考書はおっきいサイズだから下にくるのはイイとして、教科書は大きさも厚さもマチマチなんだもん。これじゃ、入るものも入んないよ~。 これにまだ、筆箱とかも入れにゃぁならんのに……。 机に座ったままのわたしが上目で前を見てみると、すぐそこの出入り口から、カバンを2個ずつ持ったクラスメート達が続々と帰宅していく。 その中の1人の女の子が、わたしに向かってバイバイと可愛く手を振りながら、小声で、 「お先にぃ、サナちゃん」 と言って、教室から出て行った。 うぉっ、ハナちゃん、あんた早いっすよ。 わたしは思わす、口がへの字になってしまう。 ふっ、やっぱもう1個カバン持って来とけば良かった。……ってか、忘れただけだなんて絶対イエナイ。 今ごろ、お気に入りのあのトートバッグは、わたしの帰りを寂しく待ってるんだろうなぁ。 ゴメンナサイ。カバンの中にカバンを入れるのが何だか可笑しくて、別々に学校へ持って行こうと思ったわたしが悪いんです。帰ったらちゃんと謝るから、スネちゃわないでね。 ワッペンいっぱいのピンクいトートバッグが膨れっ面になってるのを想像したわたしは、その可愛らしさにまた愛着が強くなるのがなんとなくわかった。 でも今日から3年間は、このコに浮気しちゃうんだよね~。わたしの目の前で大口を開けてる、この学校のカバンに。 これがまた結構デザイン良くって、一目でわたしのハートにググッときたのだった。 白地の革に茶色の縁取りがしてあるだけで、見た目はかなりシンプルなのだが、それゆえに今着ているこの独特な青いブレザーの学制服と良くマッチしてる。そして、さらにポイント高いのが、なんと学校のマークが表生地のどこにも入ってないのだ。 プライベートでも遜色なく、というより、こっちの方を使いたくなるくらいにメチャ品の良い造り。 ココの中学校が設立したとき、制服とか学用品のデザインを新鋭のデザイナーさんに依頼したというのは、この街ではちょっと有名な話。そのデザイナーさんのモットーが、シンプルだけど可愛らしく、ということらしい。 う~ん、お見事です! 大事に使わせていただきます。 あ、でも今日だけは、ヤバイくらい無理させちゃうかも……。 だから、そうならないように、今はわたしが工夫しなくちゃね。 たぶんギュウギュウに詰め込みさえすれば、教科書はこのカバン1個に全部入るはずだった。しかしそれじゃぁカバン君がかわいそうだし、なによりわたしの気がスッキリしない。難しい言葉を使うなら……り、理路整然? とした状態が、わたしは好きなのだ。 なんか理路整然の使い方、間違ってるような気がするけど。しかし、そんなことは気にしちゃいられない。 今取り組むべきは、この難問。 カバンの中は、すでに半分以上が各教科の参考書で埋められている。いかにして、この限られたスペースに教科書を入れていくか。 わたしは再度、綺麗に入るように大きさを考えながら、カバンに教科書を詰めていった。 とりあえず、数学とか英語かとサイズの大きいものを先に入れるのだが、その時点でホントはもうギブアップ寸前。 「このまま、お家にもって帰らせて~!」と叫びたくなるのをグッと抑えて、真面目に残りの教科書に取り掛かる健気なわたしはノーベル賞ものだね。 うっし! さあ次いってみよ~。 気合いを入れたわたしが次に手に取った教科書は、 「…………」 おおっと、お前さんかい? わたしは一瞬だけ、クラ~っとめまいがした。 国語さん……あんたその体、なんとかならんのかねぇ。 そう、これまで一番のネックになっていたのが、サイズはちっちゃいものの、ちょっとした辞書並みにブ厚い国語の教科書だったのだ。 まったく、キミさえいなければこんなにも苦労はしないのに。 まあ、これだけ置いて帰るという案も出なかったわけではないんだけど、それはなんかイヤだったので、最終手段として頭の片隅に追いやったのだった。 わたしは、もうそろそろヤバくなってきているカバンのすき間に、グイッとネジ込むような感じで国語の教科書をトライしてみる。 が……。 ほら、やっぱダメじゃん。 入んないことはないけど、カバン君は「苦しいですぅ!」って言ってるし、順番待ちしてる他の教科書はまだ5冊ほど残ってる。こりゃぁどう考えても非常にキビシイ。 イッキに意気消沈のわたしは、ついさっき入れたばかりの国語やその他の教科書を取り出して机の上に戻した。 さてどうするべか……。 一応、最終手段があるから、このままお家に帰れないってことにはならないけど、なんかなぁ。 せっかくの新しい教科書だもん。ちゃんと持って帰って、一通りは目を通しておきたいじゃない? 特に国語の教科書なんて、楽しいお話がいっぱい載ってるかもしれないのに。 ここは恥を覚悟で、先生からなにか代わりになる入れ物を貸してもらおうかな? でもなぁ、入学初日から忘れ物しやすい生徒だって思われるのも、ちょっとね。 他に良い案がないか考えてみるが、呆れるくらいに全然浮かんでこない。 ガックシだな。わたし自身に。 誰か助けて~。……って、ところでさぁ、さっきから妙にアツ~い視線を感じるのはわたしだけ? なんか、見おろされてるっぽいし。 すぐ左横に人が立っているのに気付いたわたしがチラッと横目で見てみると、わたしと同じスカートをはいた足が見えた。 うひゃ~、誰だろう? もしかしてわたし、目を付けられてケンカ売られちゃったりするのぉ? サナ、ピーンチ! しかしそれでも見ないわけにはいかないので、わたしは恐る恐る、でもガンバって表情には出さないようにしながら、視線の方に顔を向けてみた。 あっ。 すると、な、なんと、わたしはその人を知っていた。ってゆーか、クラスメートになったんだから知らないわけはないんだけどね。それよりず~と前から、よ~く知っていたのだ。 さ、咲真さんだっ!! 女子のあこがれの咲真恭子(さくま きょうこ)さんだ。 同じクラスになって実はひっそり喜んでたその人に、わたし、もしかして見られちゃってる? ああ、咲真さんにならケンカ売られたっていいかも。 もうどうにでもして~って、あれぇ? なんかその凛々しい顔が、ちょっとずつ遠ざかっていく気がするんだけど……。 あ、なんだ、わたしの体が、椅子が、傾いていってるんだ。 わたし、このまま後ろに転げ落ちちゃうんだ。 なにもそこまで驚かなくったって……。 わたしは自分自身にツッコみながら、意識がスローモーションになってるのを感じた。 いっつもコケちゃう時ってスローモーションになるんだけど、今日のは特に遅い。 ゆっくりゆっくりと、咲真さんの顔が白くかすんでいくこの状態に名前を付けるとしたら……ホ、ホワイトアウト? うわぁ~、わたしってばカッチョいい~。 って、そんなことはどうでもいいから、誰か……。 誰か、た~す~け~て~。 |
|
「ありがとね」 それは、わたしの隣を歩く咲真さんへの感謝の言葉。 彼女とはひょんなことから一緒に帰ることになって、こうして今朝初めて登校してきたばかりの道を、来た時とは反対方向に、お家に向かって歩いているところだった。 あの後いろいろあって、わたしの方から「良かったら一緒に帰らない?」って誘ったのだ。 って、ホントは、わたしがムリやり付き合ってもらってるだけなんだけどね~。 だって咲真さんってば、ひっくり返りそうになったわたしの腕をつかんでカッコ良く助けるやいなや、さっさと1人で帰ろうとするんだもん。お礼の言葉だけはちゃんと言っとかないとね。 それに彼女、わたしが前々から一度はお話をしてみたいと思ってた人だし。 咲真さんは小学校の時から運動会とかマラソン大会とか、そういった体育系の行事ではいっつもヒーローで、わたしだけじゃなくて周りの女子たちのあこがれだったのだ。 男子顔負けの足の速さで、かけっこでも大差で1着なんてのは当たり前だし、なんか陸上クラブにも入ってるみたいで、県大会とかスゴイ人が集まる中でも成績良かったみたい。 それにテストの点数だって悪くないって噂聞くし。 わたしなんて運動オンチだし、テストはチョー普通だし、取り柄といえば……取り柄といえば……。 と、取り柄!? ヤバイ、わたしなんにも取り柄ないや。 あっ、友達がみんないい人ばっかり……って、それはわたしの取り柄じゃないか。あはは。 ま、まあ、そんなわけで、いち咲真さんファンとして、お互いの家の場所がそんなに離れてないのを知っていたわたしは、まるで旅一座の人気俳優のように颯爽と去ろうとする咲真さんの腕に、必死にすがりついて引き止めたのだった。「待っておくれ、旅のお方……」って感じでね。 でも彼女は、145センチくらいしかないわたしよりケッコー背が高く、しかも体力もあるから歩くのもちょっと速い。一緒について歩くだけでやっぱり大変だ。荷物の教科書も重いし。 まだ学校を出たばっかなのに、すでに置いてかれそうなフンイキ。 そんな中、 「だから、もういいってば」 咲真さんがピタっと足を止め、こっちを振り向いてそう言葉を返してきた。なんだか困ったような顔で。 う~む、ちょっとしつこく言い過ぎたのかな? そりゃぁ、さっきので20回くらい目の「ありがとう」だけどさ、でもだって、咲真さんはわたしの命の恩人だもん。一生ただ働きしろって言われてった断れないくらい感謝してるんだよ。 だから、わたしは首を左右に振った。 「いくない、いくない。わたしはこの恩は、ゼッタイに忘れないよ。なにがなんでも、お返しさせてもらうから覚悟しといて」 「か、覚悟……」 「そうだよ。わたしはそれだけのことをしてもらったんだからね」 そのわたしの言葉を聞いた彼女は、 「そんな、大袈裟な」 とつぶやいて、軽くため息をついたみたいだった。 いひひ、ごめんね。 しかしなぜ、わたしがそんなにも大げさに感謝してるのかというと、実はもう1つの大きな大きな理由があったからで、それは……。 重い荷物でもう腕がきつくなっていたわたしは、足が止まったのを機に、学校のカバンを右手から左手に持ちかえた。そして、よっこいせっと背中の黒いリュックを背負い直すと、教科書同士の擦れ合う音が聞こえた。 そう、このリュックサックは借り物なのだ。誰の? って、もちろん咲真さんの。 わたしを助けた彼女は、まず「大丈夫?」ってとりあえずわたしの身を心配してくれたんだけど、まだ散乱していたわたしの机の上の教科書が気になってたようだった。だから、わたしは助けてもらったついでに恥もかき捨て、相談にのってもらおうと、予備のカバンを忘れたことを打ち明けたのだ。 すると、いともあっさり。「私、持ってきてるけど使わなかったから……」って、自分の学校のカバンから、この黒いリュックを引っ張り出して貸してくれたのだった。 で、その後はさっき説明したみたいに、「返してくれるのはいつでもいいから」って言って帰ろうとした咲真さんをわたしが引き止めて、現在にいたるというわけだ。 でもあれは今思い返してもホント、びっくりしたなぁ。 わたしなんて、ただでさえ教科書入れるだけで苦労してたのに、同じ造りのはずの咲真さんのカバンにはそれが楽々全部入ってたんだもん。しかもリュックまでもが。 あれはもう奇跡としか思えなかったね。 いくら彼女のカバン君がそれなりの太っちょさんになっていたからといって、どうやって詰めればアレが全部収まるのか……いろいろ考えみたんだけど、わたしの頭じゃ全くわかんない。 一応、聞いてはみたんだよ。「咲真さん、教科書全部入れたの?」って。 そしたらなんて言ったと思う? 「考え事してたから覚えてないけど、多分入れたわよ」だって。 信じらんないよね。あのカバン、絶対に特注品だよ、わたしの予想じゃ。それとも、わたしも考えごとしながらだったら、入れれてたのかなぁ? う~む……。 ま、どっちにしても、それはもう解決したんだからイイよね。 それより、わたしにはさっきからず~っと解決したかった、ちょっとした違和感があるんだけど……。 「ね~え、咲真さん」 「ん、何?」 「あのね、せっかくお友達になったんだから、名字で呼び合うのってらしくなくない?」 「えっ?」 友達同士、名字で「さん」付けなんて他人行儀っぽくて、わたしはなんかムズムズするのだ。 「だからさぁ、わたしのことはサナ、でいいから、咲真さんのことをキョウちゃん、とかって呼んでもいい?」 わたしがそうお願いすると、咲真さんは、 「え、え~~っと……」 と、ダメなんだかオッケーなんだか、分かりづらい顔をしてしまった。 あらら、わたし、そんなに難しいこと言ったっけ? ダメなら仕方ないんだけど、それとも前から呼ばれてるあだ名とかあったのかな? 影でこっそり見てただけで、わたし、咲真さんのこと、そこまでよく知ってるわけじゃないし。 「イヤならいいんだよ。それか、キョーコちゃん、の方が良かった?」 念のため、わたしは違うふうに聞き直してみた。 が、 「あ、嫌ってことはないんだけど……でも……」 と、やっぱり煮えきらない返事。 どうしたんだろう? 咲真さんって、もっとハッキリしてるってイメージがあったんだけどなぁ。今日は調子が悪いのかな? そういえば、まだ一回もちゃんと笑ってくれてないし。 もしかして、わたしがムリに誘ったのがマズかったのかも……。もしそうだったら、ガーーンだよ。反省しなくちゃ。 あ、それか実は「私、名字で呼び合う派だから」とか、咲真さんっぽくカックイーこと言っちゃうの? それはそれで、わたしも賛同しちゃうよ。わたしは大好きだけど、いまどき「ちゃん」付けなんてハヤらないもんね。 なんて、わたしがいろいろと考えをめぐらせていると、咲真さんが、 「私はなんて呼んでもらっても構わないんだけど……」 とのこと。 な~んだ。 「よかったぁ~。断られたらどうしようって思っちゃったよ。んじゃあ、ここで立ち止まってるのも変だから行こっ、キョウちゃん」 わたしは、ほんの少しだけ前に出ていた咲真さ……じゃなくて、キョウちゃんを追い越して、先に歩き出した。 もちろんココはみんなの通学路なので、止まってるわたしらの横を通りすぎて行く他の新入生と、その親御さんやクルマが少なからずあった。いつまでも石みたいに固まってるわけにもいかないのだ。 それに、最初だけでも少しくらいフライングしなきゃ、リードされっぱなしじゃ悔しいもん。 意気揚揚と足を踏み出したわたしは、このままずっとキョウちゃんを先導しちゃおうかしら? なんて、大胆なことも思っちゃったりして、カバンを持ってない方の手を大きく振って、歩幅もいつもより大きめになる。 さあ、このサナ隊長について来るのだぁ。 …………。 って、あれれ? もしかして……ついて、来てない? わたしはもう10歩くらいは歩いてるのだけど、背中からは、キョウちゃんがついて来ているような感じがまったくしない。 キョウちゃんどうしたの? はやく追って来てよ~。 不安になったわたしは、ちょっと歩くペースを落としてみる。 …………。 それでまた10歩くらい歩いたけれど、まだ反応がない。 どうしよう、どうしよう……。すごく後ろを振り返えりたいけど、振り返っちゃうとなんだか負けのような気がするし。でも……でも……。 寂しいのはヤだよ~。 「咲真さぁ~ん」 けっきょく振り返ってしまったわたしは、まだ慣れてないのもあって、言い出しっぺなのについつい名字で名前を呼んで、なぜかまだ同じ所で立ちすくしていた彼女の元へ走って引き返した。 が。 カバンが重くてバランスがおかしくなってたのか、わたしの足が勝手にもつれる。そして、 「あっ、あっ……」 目の前の景色が、また白くかすんで傾いてく。咲真さんの姿も傾いてく。 でも本当に傾いてるのは、そう、わたしの体だけ。 そのわたしに急いで近づいて来る咲真さんの手が、必死に伸びてくるのがぼやけて見えた。 キョウちゃん、助けてっ! けどその距離じゃ全然届かないのが、このわたしにも簡単に理解できた次の瞬間、 「ぅあっ!!」 …………い、痛い。 両方の手の平と、どっちかのひざが、ジンジンする。 「痛いよ……」 と同時に、胸の奥の底の方から込み上げてくる、あのイヤな感覚があった。 「だ、大丈夫っ!?」 どこからかキョウちゃんの心配する声が、ぐわんぐわんする頭に響く。 「……ぅ、ぅぅ……」 ダメ、泣いちゃダメ、泣いちゃダメ。泣いちゃダメ、だけど……。 声は必死に押し殺したけど、涙だけはどうにもならない。一生懸命こらえようとするんだけど、わたしの意思とは関係なく目頭が一気に熱くなってくる。 そして、わたしのガマンも、もうきかなくなり涙が……。 涙は、だらしのないわたしをあざ笑うように、大量に、ただただこぼれ落ちてきた。 「サナちゃん……」 「……ぅぁ……ぅう、ひっ……ぅぅ……」 あぁ、キョウちゃんに「大丈夫だよ」って言わなきゃなんないのに、「心配いらないよ」って笑って答えなきゃいけないのに……喉がつまって言葉が出てこないよ~。せっかく下の名前で呼んでもらったのに、返事ができないなんて……。 キョウちゃん、キョウちゃん……友達になったばっかりなのにもう迷惑かけちゃって、ごめんなさい。 ごめんなさい。 わたしは一時、顔を上げることさえできなかった。 |
|
「あのね、せっかくお友達になったんだから、名字で呼び合うのってらしくなくない?」 「えっ?」 ちょっと待って。今……何て言ったの? と、友達って? 私は自分の耳を疑ったが、まともに聞き返す勇気もなかった。 今更ながら、彼女と共に帰宅している事を後悔し始めていたその時に言われたものだから、私はいっそう動揺してしまったのかも知れない。 2人で学校を出てから、まだ10分近くしか経ってないが、その間に私も頭を過ぎらなかった訳ではない。成り行き上とはいえ、一緒に帰宅する事になったこのクラスメートと友達になれたら……と。 しかし、とても今風な理解し難い言動と、これまでの路程でしつこく繰り返された「ありがとう」の連呼で、私は彼女のことを敬遠したい気分になっていた。 感じは悪くないんだけど……変わった女の子。 それが私の、浅木沙那さんに対する第一印象だった。 何もしてないのに勝手に引っくり返りそうになるし、偶然にも家が同じ方向だったから良かったものの、「一緒に帰らない?」などと私を誘うし、挙句の果てには、覚悟してお礼を待っていなければならないらしい。 一体、彼女は私をどうしたいというのだろう……。 というより、私を友達と言ったこの女の子と、これから本当に付き合っていくの? 自分の事なのに、あまりの急展開のせいで、まずそれが分からなくなっていた。 「だからさぁ、わたしのことはサナ、でいいから、咲真さんのことをキョウちゃん、とかって呼んでもいい?」 そんな、どこかで聞いたことがあるようなクサイ台詞を、はっきりと恥ずかしげもなく口にした彼女に、 「え、え~~っと……」 私は曖昧な返答しかできなかった。 「イヤならいいんだよ。それか、キョーコちゃん、の方が良かった?」 「あ、嫌ってことはないんだけど……でも……」 そういう問題じゃなくて、え~っと、こういう時はなんて答えればいいの? 私はまだ答えを出せる段階じゃないのよ。友達って、もっとお互いを良く知ってからなるものじゃないの? もう少し考えさせてよ。 でも「考えさせて」と言えば、彼女に失礼な気がするし、だからと言って軽々しく了承はしたくない。 ただ、呼ばれ方になんかこだわらないから、とりあえず、 「私はなんて呼んでもらっても構わないんだけど……」 今は頭の中を整理する時間が欲しいのよ。 私は、自分の思っていることを伝えられないもどかしさを感じた。 そんな私に浅木さんは、 「よかったぁ~。断られたらどうしようって思っちゃったよ」 ホッとしたようにそう言ったかと思うと、今の私には痛いくらい明るい調子で、 「んじゃあ、ここで立ち止まってるのも変だから行こっ、キョウちゃん」 と声をかけてきて、さっさと1人で歩き始めた。 あっ、待って! 「…………」 しかし、なぜか私の声は出ないし、足は追い掛ける事もしない。頭はボーっとして、まるでめまいのような錯覚を起こしていた。 青いブレザーの制服が、ひょこひょこと上下しながら徐々に遠ざかっていく。 あぁ……行ってしまう。 春の日中の光を浴びて、妙に意識がもうろうとする中、私はその背中をぼんやりと見つめる事しかできなかった。 どうして追い掛けていかないの? さっきまで、あんなに友達がほしいって願ってたんじゃない。友達って言ってくれてる女の子が、すぐ目の前にいるんじゃない。その彼女に何か不満でもあるの? 不満? ……ううん、不満はない。 確かに、彼女の発言や行動はあまり理解できないけど、そんなのは誰にだって多少はある当たり前のことなんだし、それに、裏表のある性格にも見えない。きっと私なんか相手にしなくてもいいくらい沢山の友達もいて、私もその輪に入れるものなら入ってみたい。 だけど……。 不満はないんだけど、私は……そう、不安、なのかも知れない。 何に対して不安なの? 何って……分からないわよ、そんなの。 お父さんとは、ちゃんとそれなりに決着は付けたつもりよ。私に繋がっていた大きな枷は、もうとっくに外れてるのよ。 中学生になった私は、もう独りで何処へでも歩き出せる筈よ。何にだって変われる筈なのよ。 なのに……。 なのに、何でこんなにも足が動かないのよっ! 「咲真さぁ~ん」 っ!! その声で、私は我に返らされた。 いつまで経っても追いついて来ない私を心配したのか、10メートル以上は離れた先で振り返った浅木さんは、こちらに走って引き返そうとしていた。 だが、私はその瞬間には分かった。 あっ! やばい、コケる!! それは、私が陸上の練習中に人がコケるのを良く見ていたし、自分でもいっぱいコケた経験があるから分かったことだった。 私の体は考える間もなく動き、走り出していた。先程までのわずらわしい思いは、とりあえず後方へと置き去りにして。 「あっ、あっ……」 彼女の体は思いのほか倒れ込むのが早く、必死に伸ばす私の手は間に合いそうにない。 お願いだから、ちゃんと受け身とってよ。 「ぅあっ!!」 浅木さんは前方にバタッと倒れ込んだ。それはちょうど四つんばいの状態で。顔面から、という悲惨な状況だけは、どうやら避けてくれたようだが。 私はそのまま彼女のそばまで駆け寄る。 「痛いよ……」 分かってるわよ、それくらい。コケたんだから当たり前でしょ。 別に親しい訳でもない彼女に、私の口はそう言いたくなる。が、結局は、 「だ、大丈夫っ!?」 という月並みな言葉をかけるしかなかった。 当の本人は今にも泣き出しそうに、 「……ぅ、ぅぅ……」 と、おえつにも似た小さなうめき声を出している。 しかし勢いはさほどついてなかったので、そこまで大した怪我にはなってないだろう。 外見から具合をみて、おそらくは手と膝を打ったに違いない。が、あのコケ方なら悪くても打ち身と軽い擦り傷程度。医者ではないから詳しくは判らないが、骨にまで影響していないのは確信があった。 その為、かけた言葉とは裏腹に、私は少し安心する。 浅木さんって、いっつもこんなそそっかしいのかしら? もう少し慎重に行動してよね、まったく……。 その時、頑張って抑えていたのか、少し遅れた涙がポタポタッと地面に落ちたのに気付いた。 ああもうっ、なに泣いてるのよ。まるで誰かさんみたいじゃない。 ……えっ。 誰かって……あっ、アヤ。 それは、私と5つも歳の離れている妹・綾子(あやこ)だ。 まだ四つんばいで下を向いたままの浅木さんの姿が、その私の妹の姿とダブって見えたのだ。 アヤの性格は至って大人しくかなり慎重派の筈なのだが、まるでそれが癖であるかのように良くつまずいては、今の浅木さんみたいに泣くのだった。そんな時は、普段からアヤの面倒を両親から任されている私が、決まって慰めるのである。 中学1年生と小学2年生が同じに見えるだなんて、私も変よね。 目の前でクラスメートが泣いているというのに、そのいつもの情景と重ねた私の気持ちは、今日一番に落ち着き始めていた。 浅木さん、立てるかなぁ? 見知らぬ通行人が、何事か? と様子を窺いながら通りすぎて行く。 まぁ、それを気にしている余裕はないが、私もいつまでも泣かれていては困るので、どこか休める所まで移動したかった。 まずは立てるかどうかじゃなくて、立ってもらわなくては。 そう思った私は、浅木さんに呼びかけた。 「サナちゃん……」 なぜか、彼女の望んだ下の名前がすらりと自然に出てきたのには、自分でも驚いた。妹以外を「ちゃん」付けで呼んだことなど、一度もないからだ。 なんか、アヤを相手にしている時のような不思議な感じね。だからって、浅木さんがアヤに似てるって訳でもないけど……。 「……ぅぁ……ぅう、ひっ……ぅぅ……」 浅木さんは泣いているせいで、まだまともに言葉にならないようだった。 起こしてあげてもいいの、よね? そのおえつが、私の呼びかけに対する返事のような気がしたのもあるが、やはりさっさとココから移動したい私は、無理やりにでも彼女を立たせたかった。 そうと決まれば、私の行動は早い。 浅木さんの隣で私も膝をつくと、 「ちょっとゴメンね」 断りを入れてから、私の貸したリュックに左手を掛けて促した。 「右手、上げてもらっていい?」 すると、返事はないものの、浅木さんは素直に右腕を曲げようとする。 よしよし、いい子いい子。 私はバランスが崩れないように彼女の体を支えるながら、まず右側からリュックの肩掛けを外す。そして、片方が外れてしまえば、後は反対側にゆっくり落とすようにすればいい。私はそうやって、浅木さんの背中からリュックを下ろさせた。 後は、と……あれっ? 私の鞄は……。 いつの間にか自分の鞄を見失っていた私は、キョロキョロと首を回して辺りを探る。 ……あ、あんな所に。 その鞄は、まだ私が走り出す前にいた所に、ぽつんと転がっていた。どうやら走った時に、とっさに落としてしまったらしい。 「ちょっと待っててね」 浅木さんにそう告げた私は、急いで取りに行って鞄をつかみ上げると、すぐさま彼女の元までまた走って返った。 そして、せっかく拾ってきた自分の鞄を再度地面に置き、今度はさっき彼女から外したばかりのリュック拾って、本当の持ち主の私が自ら背負う。 さらに、自分の鞄を拾って右脇にグッと挟み込むと、そのまましゃがみつつ、浅木さんの手から離れていた彼女の鞄も右手で拾い上げた。 ぬぐぐっ、流石に2人分は、お、重い! だけど、ここは私しかいないんだから、弱音は吐けないわよ。 怪我してるかも知れない人に、重い荷物を持たせる訳にはいかない。 私がこんなに頑張ってるんだから、あなたも少しは頑張ってよね。 見ると、浅木さんはもう涙を流してはいないようだったので、私はわざと自由に使えるようにしていた左手を彼女に差し出した。 「ほらっ、立てる?」 彼女は少しだけ顔を上げて、小さくうなずく。 よし。それじゃいくわよ。 「ちょっと行った所に、公園があるのは知ってるわよね。あそこで傷を診てあげるから、その間だけ我慢して歩いてもらえる?」 そうお願いしながら、私は上半身を倒して、自分の左腕を浅木さんの右脇を絡ませた。 今は手加減できないから、びっくりするかもしれないけどっ!! 思いっきり気合を入れた私は、腹筋と背筋を全開にして倒した上半身を一気に起こす。 「きゃっ!」 案の定、浅木さんは悲鳴をあげた。 まぁ当然かな。 両手と両膝をついた四つんばいの状態から、一瞬で直立の状態まで起き上がらせたのだ。 本当は、もっとゆっくりと手加減できるのだが、2人分の鞄があっては仕方がない。こうでもしないと逆に疲れて、公園へ着く前に私がバテてしまう。 それに、大した怪我でないのは判っていたし、浅木さんの沈んだ気持ちを一転させるのにはちょうど良かった、という思惑もあった。 私の判断は、間違ってなかったのよね……。 もしかしたら、この事で浅木さんに嫌な思いをさせていたかも知れないと思った私は、左肩に触れるくらい近い所にある彼女の顔色を窺ってみた。 が、 「だ、大丈夫?」 「へっ!? あ、何? 誰? えーと私は……」 浅木さんは、自分の身に何が起こったのか解からないような様子で、目をキョトンとさせ口をあんぐりと開けた可笑しな表情で、呆然としていたのだ。 「しっかりしてよ」 「あっ、ごめん、咲真さん。キョウちゃん。あの……ごめんなさい」 「別に謝らなくていいから」 「えと、そうじゃなくて」 浅木さんは制服の袖で涙を拭いながら、何かを言いたげにしたが、私は無視した。 「公園まで歩くけど、足、痛くない?」 私は立ったまま、上から彼女の膝を覗き見ながら訊ねる。 「あ、うん、少し痛い……」 「ああ、ちょっと血がにじんでるわね」 でも、酷いものではないわね。不幸中の幸いってとこかな。 「じゃぁ私がこのまま支えて行ってあげるから、自分の痛くないペースで歩いて」 「う、うん」 そして私達は、ここから程遠くない所にある公園まで、ゆっくりと歩き始めた。 と、歩き始めてすぐに、浅木さんがあることに気付く。 「……あっ、カバン」 「私が持ってる」 私は端的に答えた。 「ご、ごめん、なさい。ホントに……」 もうっ、面倒くさいなぁ。謝らなくていいって言ってるのに。 「いいから、悪いけど、公園着くまで黙っててもらえる?」 「……うん……」 すると、浅木さんはションボリしたように、下を向いてしまった。 ちょっときつく言い過ぎたかな。まぁいいや、今はそんなこと考えていられない。 私は苛立っていた、というか、鞄を落とさないように集中していて、まともに相手をすること自体がつらかったのだ。 なにせ、右半分は2人分の教科書の重さに耐えつつ、左半分は人を1人支え、ペースも合わせなければならないという状態。私の神経はもう一杯一杯で、かの聖徳太子でさえこれ以上の事を同時に行なうのは厳しいのではないか、と思える程。 まぁ、ある種の修行みたいなもんだと思えは、まだ多少は楽かな。 しかしそんな下らない雑念だけは、公園までの道中、どうしても湧き止むことはなかった。 |
|
しばらく、と言っても、5分弱くらい。 その間に私達2人は一言も会話を交わすことなく、目的地にたどり着いた。 今はちょうどお昼時だからだろうか? そこは、誰もいない殺伐とした景色が広がっていた。普段からそこまで人の集まる公園ではないが、誰もいない公園というのは妙に寂しいものである。 さっそく、私は中央にある水飲み場へと足を向け、浅木さんを誘導した。 「段差があるから、気を付けてね」 そして、どこの公園にもあるような、上は噴水式で横からは手足を洗う蛇口が付いている円柱体の水道のそばで、私は浅木さんの腕の支えを外す。 「じゃぁ、ここで待ってて。鞄、下ろしてくるから」 ふぅ、やっと両手で持てる。 右脇に挟んであった自分の鞄を左手に持ち替えた私は、疲れていたが、公園脇に点在するベンチの1つまで走った。早く、この重い荷物から開放されたかったのだ。 私はそのベンチの前まで来ると、地面には落ちないように、しかし乱暴に、ドカドカッと鞄とリュックを放り投げ……た時には、もう手遅れだった。 あっ、しまった! 自分のじゃないのもあったんだった。 とっさに振り返って浅木さんの方を窺うと、彼女は水道の水を出して手を洗ったり、喉を潤していたりしていた。 見てたかな? ……いや、ちゃんと謝ろう。 水飲み場へと戻った私は、浅木さんの前で、 「ごめん。浅木さんの鞄に傷つけたかも知れない」 と正直に謝った。 私は、ある程度、嫌な顔をされるのを覚悟していた。が、 「ん、ありがと」 彼女から返ってきた言葉は、またしても、私には理解不能の一言だった。 はぁ? なんでそこで、ありがとう、な訳? 自分の、しかも真新しい物に傷がついたかも、というのに……やっぱり変わった女の子。 ともかく怒ってはいないようだったので、傷を診るのが先決だと割り切った私は、 「足出して」 手足洗い用の蛇口の横にしゃがんで、そう指示した。 浅木さんは自分でバランスを取りながら、怪我をした右足を斜めに持ち上げる。 「ちょっと濡れるけど、いいわね」 「うん」 その返事を待ってから、私は蛇口をひねって水を出すと、ほぼ直接、その血や砂で汚れた膝にザバザバとかけた。 とすぐに、浅木さんが間の抜けた感じで、 「あ~~~っ」 と、すっとんきょうな声を出す。 流石にその声は、何に対する抗議かは解かった。 なによ。今更になって、濡らし過ぎ、とかはなしよ。それとも、脱がせてくれ、とでも言うつもり? まったく。 しかし元はといえば、私が乱雑な仕事をしているのが悪いのだから、若干開き直りつつも、とっさに彼女の靴と靴下を脱がせた。ただそこは得意分野とでも言うべきか、アヤという前例があるので、私の手際は至ってスムーズだ。 ある程度水の流れだけで、膝に付いた血や砂が落ちて綺麗になるにしたがい、そこから本当の傷口が見えてくる。と……。 なんだ、あんがい小さい傷じゃない。 汚れていると大きく見える傷も洗ってみると大したことはなかった、ということは結構あるが、浅木さんのそれは、バンソウコウ一枚で隠れそうなくらいに極めて小さな傷だったのだ。 これなら心配いらないわね。万が一、シミになったとしても、膝ならそんなには目立たないだろうし。 浅木さんの膝を洗い終えた私は、脱がせた靴と靴下を持ってその場に立ち上がり、それを前に差し出す。 「はい、自分で持って」 彼女は素直に受け取ると、落ち込んだ気分も、もうだいぶ回復してきているらしい。 「ありがと」 少し嬉しそうに微笑んで、またお礼を言った。 その笑顔を見た私は、なぜか恥ずかしくなってつい顔を背けてしまい、無言で肩を貸すことになった。 なにしてんだろ、私。どういたしまして、くらい言えばいいのに……。 別にそれは、同性がドキッとするほどの笑顔だった、という訳でもない。だけど、なんというか……その笑顔が、彼女にあまりにも似合い過ぎていたので、逆に私の方が素直になれなかったのだ。 私の肩をつかんで、少し痛そうにぴょんぴょんと片足で跳んでついてくる浅木さんに気を使いながら、私は鞄を置いたベンチまで歩いた。 「ほら、座って」 「うん」 怪我人に先に腰をおろさせた私は、また彼女の足の前でしゃがみ込むと、ブレザーの右ポケットからハンカチを取り出して、まだ水滴の付いているその足を拭いてあげる。そして、あらかた拭き終えると、今度は左ポケットからバンソウコウを取り出した。 「わっ、準備いい~」 「ああ、これ?」 私はバンソウコウのテープを外しながら、浅木さんの顔も見ずに聞き返す。 「そうそう。いくら女の子でも、普通、バンソーコーなんて持ち歩いてないよ」 「……ま、まぁ、たまたまよ。何となく入れてただけ」 少し苦しい言い訳だが、私はそう答えた。 確かに、どんなに準備のいい人でも、初めて着る服のポケットにバンソウコウが入っているのはおかしい。 しかし私は、妹という最も身近な人間が良く怪我をするせいで、これを常備しているのが当たり前になってしまっていたのだった。 「はい、これで良し。今のところはね。帰ったらちゃんと消毒して、新しいのに付け替えないと駄目よ」 「うん、ありがと」 「さてと…………よいしょっと」 やっとのことで、ベンチに腰を落ち着かせることができた私は、 「はぁ……」 と、大きなため息を吐いた。 「疲れた?」 浅木さんが靴下を履きながら、そう聞いてきた。 「そりゃぁね。もうくたくたよ」 陸上の練習でも、ここまでの疲労感はなかなかあるものではない。まぁ、あっちに比べれば、私からしたら義務感がない分、嫌な疲れではないが。 「また借りができたちゃったね」 「借り? ああ、気にしないでよ。私が勝手にした事だから。それに、浅木さんがあの時グズってたら、置いて行ってたし」 もちろん冗談だけど。 だが浅木さんは、 「マジでっ!!」 と、かなりの大袈裟に驚いたかと思うと、すぐに、ホッと胸を撫で下ろした。 「よかった~。いっつもだったグズっちゃうんだよね、わたし」 あら、そうなんだ。結構素直だったような気がするけど。 「でも、キョウちゃんにだけは迷惑かけられないって思ったら、ね」 「…………」 私にだけは……か。 多分、浅木さんにとっては特に意味はないのだろうけど、ほんの少しでも、私のことを特別な存在で見てくれているのだ。 その何気ない言葉が、私には嬉しかった。 と、いきなり、浅木さんは険しい表情を作って、 「それはそうと……」 話を切り出してきた。 「な、何?」 ちょっとビックリしたが、その表情は長くは続かないらしく、彼女はすぐに元のぽやんとした顔に戻すと、 「もう下の名前で呼んでくんないの? キョウちゃん」 私がすっかり忘れていたことを掘り起こしてきた。 そういえば、不思議と口から出たあの1回限り、ずっと「浅木さん」って言ってきたような。 でもその前に、私もハッキリさせないといけないことがあったのを思い出した。 「あの、そのことなんだけど……」 私がそう返すと、浅木さんは先の先まで読んだのか、 「やっぱり、イヤなの~?」 と、悲しそうに私の目を見つめてきた。 もうっ、まだ何も言ってないってば。意外とせっかちなんだから。 「じゃなくて、その、なんていうか……えーっと」 「ん?」 私はなかなか言いたいことが、言葉になって出てこない。 しかし、聞かずに後悔することだけは、絶対に避けたかった。 「あのね、本当に、私なんかが友達でいいの?」 やっと出てきた言葉は、たったそれだけ。でも、それが全てだった。 私みたいなつまらない人間が、本当に友達でいいのか。 「ふへっ? どーゆーこと?」 んーと、ようするに……、 「私、テレビはほとんど見ないし、漫画だって持ってないし、興味がない訳じゃないんだけど、浅木さんとかがしそうな、今時の話題にはついて行けそうにない……。私、家では、お母さんの手伝いとか妹の面倒とか、もちろん自分の勉強とかの方を優先させないといけないし……」 はぁ、せっかく友達になれそうな女の子の前で、私、何言ってんだろ……。 私は、その私自身のことを知った浅木さんがどんな答えをくれるのか、正直、考えたくはなかった。この場では「それでもいいよ」と言ってくれるかも知れないが、心の中では「なんだ、つまらない人」と思ったに違いない。たとえ、そんなことを思うような女の子には見えなくても。 ホントのところ、彼女が何を思ったのかは分らないが、私と顔を見合わせている浅木さんの目は、パッチリと大きく開かれていた。 今までは気にならなかったけど、こうして見ると浅木さんの目って、まん丸でとっても大きいのね。綺麗な瞳……。 ただ、今は、そんな純粋そうな瞳に見つめられているのが、凄く辛いのだけど。 正確には5秒もなかったであろう、小さな間。 でも私には、それが10分にも1時間にも感じられてならなかった。 と、その私が止めてしまった時間を動かしたのは、私ではなく浅木さんの方だった。 彼女は、その大きな瞳をパチパチっとまばたきした後、にっこりアーチ状に細めると、私が想像もしてなかった答えを返してきた。 「わたし、なに言われるかと思って、ドキドキしちゃった」 「えっ?」 「いっしょ一緒。同じだよ。わたしだってマンガなんてあんまし持ってないし、弟の面倒だって見なきゃいけないし、ってゆーか、あの構ってちゃんの相手してるだけで、家では精一杯だよ。今時の話題なんて全然、わたしの方こそついていけなくて申し訳ないなぁって思ってたのに」 そ、そうなの……? 「うひょ。さっそくイガイな共通点、発見!」 そして、浅木さんはまた目を大きく開けて、今度はグッと顔を寄せてきたかと思うと、私の両手を握った。 「わたしの友達って、一人っ子とか末っ子とかが多いんだよね~。なんちゅーかさ、こう姉の大変さってゆーのを分かってくれる人がいなくて、相談する相手がいなかったんだよね」 姉の大変さ、か。……なんか解かる気がする。ってゆーか、顔近いし。 「キョウちゃんってだけで100点満点なのに、そんな嬉しい特典まで付いてくるなんて、涙がちょちょ切れんばかりっすよ」 あはは、表現が古~い。 「あはっ、キョウちゃんが笑った」 えっ!? 「やった。キョウちゃんがやっと笑ってくれた。もうサイコー。今日死んでも悔いないや……」 私、そんなに硬い顔してたかしら…………いや、多分、してたんだと思う。 そうか、友達って、なんでもいいから思い切って自分から伝えないと、始まっていかないのね。やっぱり。 こんな些細な共通点だって、実際に照らし合わせてみないと解かる筈がない。特に、私みたいな口下手な人間ほど、ちゃんと伝えないといけないのに。 私は、とても運が良かったのかも知れない。 なぜなら、普通「友達」といっても、いつからそうなったのか、答えられる人は少ないと思う。けど私は、将来、「いつから浅木沙那さんと友達なの?」って聞かれたって答えられる。 今日の、まさにこの瞬間だと。 なんか、浅木さんに、大事なことを教わった気がする。ありがと、浅木さ……! 気付くと、浅木さんは握っていた私の手を放して、本当に死んだか失神してしまった人のように、ふわ~っと後ろに倒れていっていた。 「おっと!」 危ないなぁ。 私は、今日学校で初めて彼女と目を合わせた時のように、その腕をつかんで引き寄せた。 「ちょっと、ホントに気を付けてよね」 「す、すまぬ。拙者、嬉しさのあまり気が動転しておったよ」 浅木さんは、まるで人格が変わってしまったみたいに、そう口走った。 なによ、その変な忍者口調。 それにどう対応していいかわからず、私の方こそ気が動転しそうになったが、 「ってゆーか、わたしの問いはどーなったわけ?」 「はぁ?」 「いや、だからさぁ、下の名前で呼んでくれるっていう……」 あ、そっか。そういえば。 私の心配をよそに、浅木さんは勝手に話を戻した。 「場合によっちゃ、友達解消とかも……」 ちょっと、勘弁してよ。 「冗談だけどね~」 はぁ、その冗談が、今の私には一番キツいんだけど。 まぁいいや。とりあえず私の気分は、なんだか学校でぐだぐだ悩んでいたのが嘘みたいに軽いし。 私は、スッと右手を差し出した。 「よろしく。サナちゃん」 すると彼女は、とても丁寧に頭を下げて、しっかりとその手を握ってくれた。 「よろしくお願いします」 握手なんて堅苦しいって思うかも知れないけど、私にはこれくらいがちょうどいい。堅い女は堅い女らしくいくしかないのよ。 私というだけで100点満点と言ってくれた、目の前の友達のその言葉を、きちんと信じてあげる為にも……。 「じゃぁ、そろそろ行こうか」 私はサナちゃんと手が離れると、早々に、バッと立ち上がった。 やっぱり、まだ少し恥ずかしさが残っていて、にやけたように歪んだ私の顔を見られたくなかったのだ。 いいのよね、私。これで、本当に良かったのよね。今更になって後悔なんて、絶対できないわよ。覚悟はいい? 恭子。 大丈夫、わかってるわよ。後悔なんてする訳ないじゃない。だって、お父さんでも誰でもない、私が自分で決めたんだから。やっと動き出した足を、そんなに簡単に止めたくはないわ。 それに、ちょっと変わった女の子だけど、サナちゃんとなら上手くやっていける。 理屈抜きで、そう思えるから……。 「あっ、待ってぇ~」 突然立った私に焦ったのか、それに続いて急いで立ち上がろうとしたサナちゃんだったが、 「痛っ!」 彼女はまた、ベンチにドスンと腰を落とした。 「そっか、膝を打ったんだったわね。立てそう?」 「ん、がんばってみる」 サナちゃんは確認するように、ゆっくりゆっくり膝を曲げ伸ばしして、 「うん、大丈夫っぽい」 心配そうに窺う私に、そう応えた。 耐えれない痛みではないみたいね。だけど……。 「そう? じゃぁ、リュックだけは私が持ってあげる。途中までだけど」 私は、サナちゃんがこれから背負おうとしていた私が貸したリュックを、有無を言わさずに奪って、ひょいと背負った。そして、自分の鞄を持つ。 「キツかったら言ってよ。また、肩貸すから」 膝を気にしながら、そーっと立ち上がったサナちゃんに私が言うと、彼女は嬉しそうに微笑んだ。 「うん。ありがと」 「どういたしまして」 |
|
「ってことは、何年生?」 「えっと、今日が始業式の筈だから、今日から2年生」 「じゃぁ、うちと2つ違いだね」 「へぇ、弟さんは4年生なんだ」 「あはっ、あんなのに、さん、なんて付けなくたっていいって。だってもう4年生なのに、まだたまにわたしと一緒に寝たりするのよ~」 「ホントに? うちじゃ、絶対ありえないわ。あんまり甘やかすなって言われてるから。私も物心ついた時から、独りで寝てた気がするし」 「うはぁ、スゴい。わたしもたまに、お母さんと寝たりするのに……」 あはは、それはそれでスゴいと思うけど。姉弟似たり寄ったりね。 「あぁぁ、いま笑ったでしょ~」 「えっ、笑ってないって」 「いいもん、どうせわたしは甘えん坊だもん」 そうやって私と姉弟談議するサナちゃんの膝の痛みは、一時的なものだったらしい。時おり、しかめっ面を作ることもあるが、歩きながら普通に会話をする余裕があった。 今はちょうど、学校周辺の住宅地を抜ける頃。 そろそろ見えてくる交差点を曲がると、花屋や酒屋、玩具屋やコンビニなどが並ぶ、ちょっとした商業地に出る。ただ街自体が非常に小さいので、テレビで見るような高層ビルなんかは到底お目にかかることはできなかった。 私達の住む家は、その店舗の並びをしばらく行った先ある、また別の住宅地だ。 ちなみに、私とサナちゃんが通っていた、そして、それぞれの妹と弟が通っている小学校は、その住宅地を挟んで反対側にあった。 アヤ、大丈夫かしら……。もうそろそろ帰ってる頃よね。また転んで怪我してなければいいけど。 私は、サナちゃんが言った「甘えん坊」という言葉に、妹の綾子のことが頭をよぎった。 両親に「甘やかすな」とは言われていても、私の可愛い妹であることには違いない。両親のいない所では、ついついお菓子を買ってあげたりだとか、宿題の手伝いをしてあげたりだとかで、甘やかしてしまうのだった。 アヤもそれが分ってるのか、両親のいない時に限って、私にべったりと寄り添ってくるのが、また可愛くて仕方がなかった。 サナちゃんのところはどうなんだろう……? あんな言ってても、やっぱり弟は可愛いんだろうなぁ。まだ一緒に寝たりするくらいだから。 「ねぇ、サナちゃん」 「ん?」 「やっぱり弟って、可愛い?」 私がそんな質問をすると、なぜか彼女は、眉間にシワを寄せて、 「むっ」 と私をにらんだ。 あら? そんなでもないのかしら? 「可愛い? あの憎たら坊主が!? いっつもわたしの邪魔してばっかで、うっとーしいったらありゃしない。おちおちお風呂も入ってらんないよ」 「た、大変そうね……」 まるで吐き捨てるようにぼやいたサナちゃんだったが、次の瞬間には、吊り上げていた目を垂らして、 「でもそれがまた可愛いんだよね~」 と、にへらと笑った。 そして、とても楽しそうに目を細めて、その時の様子を語ってくれた。 「さすがにもうお風呂は一緒に入んないけどさ、どっちが先に入るかって時に、わたしが先に入るって言うと、セイくんも先に入るって言うし、じゃぁ後でいいよって言うと、僕も後でいいよ、だって。そんな感じでお風呂前に、1時間くらい遊んでるの」 はぁー、たったそれだけで1時間も遊べるなんて、なんか毎日が楽しそうだなぁ。 「あっ、セイってのは、弟の名前ね」 「うん大丈夫、話しの流れで分ったから。……でもそれだと、お母さんとかに怒られたりしない?」 1時間もそんなことしてたら、うちだったら間違いなくお父さんのゲンコツの後、長い説教だと思うけど。 そんな私の質問に、サナちゃんは、 「そうそう、どっちでもいいから早く入んなさーい! って、お母さんに怒られちゃう。えへへ」 と、気恥ずかしそうに頭をかいた。 やっぱりそれくらいが普通よね。うちのお父さん、B型のくせして細か過ぎるのよ。本当に、私もその血を受け継いでるなんて思えないわ。 私は、そんなうちの家庭事情をサナちゃんに愚痴ってしまおうか……と一瞬思ったが、今するべき話しじゃないと思いとどまって、話を先に進めた。 「それで、どっちが先に入るの?」 「うん、結局は、わたしがセイくんを脱衣所に押し込んでおしまい」 「あはは、押し込めちゃうんだ」 「だってそうでもしないと、いつまでたっても入ってくれないんだもん」 そして、サナちゃんは最後に「やれやれ……」という風に肩を落として、疲れたような素振りを見せた。 楽しそうではあるけど、男の子の相手をするのは大変そうだなぁ。もし、アヤが弟でやんちゃな性格だったら……。 想像した私は、体験してもいないのに、同じく疲れたような気分になった。 はぁ、サナちゃんには悪いけど、うちは妹で良かった。 つくづくそう思ってしまって、あんな厳しい両親であっても、妹を生んでくれたことには感謝しよう、と、先ほどこぼれ落ちそうになった愚痴を改め直した。 「んで、キョウちゃんとこは、どうしてるの?」 「えっ、何が?」 述語も無く、サナちゃんがいきなり話を振ってきた為、私は何の事だかさっぱり分からなかった。 「んー、だから、キョウちゃんは妹の……妹の……名前は?」 「綾子」 「ありがと。で、綾子ちゃんとは、お風呂はどうしてるの?」 ああ、そういうことか。まったく、ちゃんと言ってくれなきゃ分んないじゃない。 「えーっと、アヤはまだ小さいし、心配だからね。今のところ、必ず私と入るようにしてるわよ」 風呂場で滑って頭でも打ったりしたら、とんでもないし。 「そーなんだぁ。ふ~ん……」 それに実は、うちの母の方がかなりの倹約家で、私とアヤが一緒にお風呂に入るのは、光熱費の節約の為でもあった。 どのくらいの倹約家なのかというと、使ってない部屋の電気を付けっ放しにするのは、もちろん言語道断だが、たまにテレビを見る時もボリュームを極力小さくするという熱の入れよう。また、どこぞの引出しを開けると、いずれ何かに使えそうな様々な物が、綺麗に整理されてしまわれていたりする。 だからなのだろう。両親そろって細かい性格の者同士なので、2人の夫婦ゲンカを見ることは、ほとんどなかった。 会話は少ないけど、それなりにお似合いの夫婦よね。ま、そこに生まれてしまった私の運が悪いだけか……。 ……ん? ふと気付くと、私達は曲がり角である交差点を目前にしていた。私達のように中学校から来た場合、左の角はちょうど民家の高い塀のせいで見通しはあまり良くないが、初めて出くわす信号機付きの交差点なので、目印としては非常に分かりやすい。 ここを左折すると、後は私達の住む住宅地まで一直線だ。当然、サナちゃんも道は分っている筈である。 元々サナちゃんよりも歩道の左側を歩いていた私は、別段、彼女を誘導することもなく、そのままスッと体の向きを変えて左に曲が……ろうとしたのだが。 サナちゃんはうつむき加減で、何やら考えごとの最中らしい。 「うんうん。そうかそうか。アヤちゃんていうのか……。なるほどね~」 そんな独り言を呟いては、曲がろうとしている私には目もくれず直進していく。 おーい、その横断歩道は渡らなくてもいいのに……って、信号、赤じゃない!! 左右から車は来てないようだったが、いつ突っ込んで来るかは分からない。私は慌てて彼女の襟元を後ろからつかんで、ぐいと引き寄せた。 「ぐえっ!」 引っ張る力が強すぎたのか、勢いあまって彼女の体が後ろに倒れそうになった為、私は自分の胸でそれを受け止めた。 はぁ……気が気じゃないわね。 「サナちゃん、そっちじゃないでしょ」 私は説いて諭すように、胸にもたれ掛かっているサナちゃんに言う。と、いつの間にか自らの体を反転させていた彼女は、私の胸に顔をうずめながら、 「うん……キョウちゃんの香り……」 などと、話の噛み合っていない意味不明なことを、くぐもった声で返してきた。 もうっ、何なのよ、それは。何よ、私の香りって……。汗臭いのならハッキリそう言ってよね。まぁ、香りって言うくらいだから、そうではないんだろうけど。 私はその言葉の真意を聞いてみたかった。が、同時に、それ以上に気になる物が私の目に飛び込んできた為、聞くのをあきらめた。 どうせ聞いたとしても、大したことではないだろうし。 「ねぇ、サナちゃん。バレッタ……」 「ん?」 「バレッタが外れかかってるわよ」 「えっ、ホント?」 体が密着しているうえに身長差も手伝って、超至近距離で彼女の頭を見る羽目になった私は、それに気づかない訳にはいかなかった。 サナちゃんは、前髪の一部を赤いバレッタで頭上に留めて、少しだけ額をあらわにしているのだが、そのバレッタが髪から解けかけていたのだ。多分、最初にコケた時に緩んでしまっていて、今回ので大きくよじれたに違いない。 「ほら、じっとしてて。直してあげるから」 そう言って、私は持っていた鞄を降ろすと、彼女の頭に両手を伸ばした。いつもアヤの髪をクシですいてあげているので、それと似たような感覚で、何気のない自然な私の行動である。 なのに。 私の手がサナちゃんの髪に、僅かに触れた瞬間、 「ちょ、ちょちょちょっと待ってぇ~」 突然慌てふためきだした彼女は、さっきまで私の胸の中で落ち着いた飼い猫のようだったのが嘘みたいに、今度は警戒する野良猫のように私から素早く離れて、ズズズっと遠ざかっていった。 何、どうしたっていうのよっ! 何か分かんないけど、流石に外れかけたままは良くないんじゃないの? 「大丈夫よ。変な風にはしないから」 私はサナちゃんをそう説得しながら、優しく催促するように手を差し伸べた。 しかし。 「うぅ……」 ある程度距離をとった彼女は、私を見据えてジッとしたまま、全く動こうとはしなかった。 …………。 はぁ、もういいや。勝手にしなさい。 「じゃぁね。先に行くわよ」 にらみ合ってても仕方がない。 業を煮やした私は、降ろしていた鞄を拾い上げると、サナちゃんに背を向けてさっさと自宅の方へ歩き出した。一応、膝の具合が良くないサナちゃんでも追いついて来れるように、ゆっくり目の速度で。 ただし、私は、彼女を置いて行くフリをしたのではない。本当に置いて行くつもりで背を向けたのだ。追いついて来るまで、途中で振り返るつもりなど毛頭ない。 あんな訳の分からないことに、付き合ってなんかいられないし。 そして、それまでサナちゃんに集中していた私の意識と視線は、その対象がなくなったことで、おのずと周りの建物へ向けられていく。先の交差点はすでに左折しているので、見通しを悪くしていた民家の高い塀は関係なく、これから歩く道筋をしっかりと拝むことができた。 今、その民家の塀が途切れて、私のすぐ左横にはまず花屋があった。そして、次のお店は和菓子屋。さらに次は眼鏡屋という風に並んでいる。また、車道を挟んで反対側のお店は、自転車屋、玩具屋、本屋という並びだ。バス停もある。 私は小学生の時、休日でさえほとんど街に出ることはなかったので、あまり見慣れた風景とは言えないが……。 そうね。これから毎日、ここが通学路になるのよね、私。 朝の登校時は、これよりもう少し先にあるコンビニ以外、全て閉店していたので感じる事はなかったものの、こうして開店された様子を見て、あらためてその実感が湧いてくる。 あっ、この和菓子屋さん、ソフトクリームもやってるんだ。今度、アヤを連れて来てみようかなぁ? そんな目新しい新鮮な感動も覚えることができた。 と、その時、誰かが後ろから、私の制服の袖を軽く引っ張った。 「キョウちゃん……」 消え入りそうな声で、私は呼ばれる。 「…………」 もちろん、誰が私を呼び止めたのかは判っている。私の名前をそう呼ぶのは、この世で1人しかいない。 ……はぁ、しょうがないなぁ。 足を止めた私は、引っ張られた方に振り返った。 見ると、案の定そこにいたサナちゃんは、右手で私の袖口を握り、左手で落ちそうになっている赤いバレッタを必死に押さえていた。 「……怒った?」 「別に怒ってないけど……髪を触られるのが嫌なら嫌って、そう言えばいいのに」 「そ、そうじゃないんだけど……」 「けど、何?」 私は問い詰めるつもりはなかったが、つい、サナちゃんの言葉尻を取って質問してしまう。 「言いたくないんだったら、それでもいいけど、そのまま手で押さえながら帰るのは、大変なんじゃない?」 私がそう言うと、サナちゃんは、 「うん……」 と短く返事をした後、いったん口を閉じて少し間を置いてから、意を決したようにまた口を開いた。 「じゃぁ、キョウちゃんにだけ見せるから、他の人には絶対ナイショにしててね」 そして、私にしか見えないような角度に頭を傾けてから、カチッと留め具を外して、ようやくバレッタを持ち上げた。 すると、そこから現れた彼女の髪の毛は……。 「こ、これは酷いわね」 私は思わず言葉が漏れる。 いや、これは本当に、人には言えないな。 「キョウちゃん、誰にも」 「分かってる、私も見なかったことにするから」 「うん、そうしてくれると、助かります……」 なぜそれを口にできなかったのか。一見しただけで理解した私は、早速サナちゃんからバレッタを受け取ると、苦労しながらも何とか元の位置にそれを留めてあげた。 「はい、いいわよ。グラグラしてない?」 私がそう訊ねると、サナちゃんは手でバレッタを触りつつ、左右に頭を振って確かめる。 「うん、グラグラはしてないけど……あっ」 それでも心配だったのか、すぐ先の眼鏡屋の店頭に鏡があるのを見つけると、足早に走って行った。 まったく、膝はいいのかしら……? 鏡の前に立ったサナちゃんは、顔を近づけてじっくりと慎重に、自らの髪が乱れていないかを確認し始めた。 私はそれに歩いて追いつく。 「どお?」 「んーーーうん、大丈夫かなぁ」 そこでやっと安心したらしい。私の方を向いたサナちゃんは、恥ずかしそうにしながらも、ニコッと微笑んだ。 そうそう、あんたは笑顔でなくっちゃ。 私はなぜか、今日初めて言葉を交わした筈の彼女に、まるで旧知の間柄であるかのような、そんな感想を思ってしまった。 私達2人は再び、並んで歩き出した。心なしか、隣合うその距離が近くなったように感じた。 そっか。どんなに天真爛漫な明るい女の子でも、悩みは悩みでちゃんとあるのね。でも、私は見なかったことにするって言ったんだから、サナちゃんの為にもさっさと忘れなきゃね。 いや、でも、あれはホントに酷かったなぁ……。 私は忘れたいのに、つい思い出して、苦笑いしてしまった。 「ねぇ、キョウちゃん」 おっと、いけない。 急にサナちゃんに呼ばれた私は、慌てて表情を元に戻した。 「な、何?」 少し声が裏返りそうになった私を、サナちゃんは不思議そうに見つめるが……特に気にした様子もなく話を進めた。 「ほらっ、あそこ見て」 そう言いながら、車道を挟んだ反対側を指差した。 ん? 私は言われるがまま、サナちゃんの指が示す場所に視線を飛ばした。 ……ああ、多分あの建物のことね。 その建物は本屋の左隣にある店舗で、外装の壁は白く、出入り口の上に横長い真っ赤な看板が乗っかっている。どこかログハウス風な可愛らしい造りをしていた。看板には丸っこい白文字で……。 MOS? ……ああ、モスか。モスバーガーね。いわゆるファーストフードってやつよね。入ったことは1回もないけど。 「うん、見たわよ。モスバーガーって言うのよね」 私は視線をサナちゃんに向け直して、きちんと見たものを伝えた。 が、彼女はそれだけでは不満らしく、ぷっくらと頬をふくらませると、 「違うよ。そうじゃなくて、その中だよ」 ということらしい。 はぁ、中……ね。 よく分からなかったが、私はもう一度さっきの建物を見た。一応、部分的にガラス張りになっていたので、中の様子もそれなりに窺える。 「ほらほら、右の方、右の方」 私を急かすサナちゃんの言葉にならって、右に……。 「あっ!」 私はやっとのことで、彼女が何を指していたのか理解した。 「同じ学校の人ね」 そこには、私達と同じ中学校の制服を着た女の子が座っていたのだ。 「そうそう。やっと分かった?」 「まぁ分かったけど、それが、どうかしたの?」 私が訊ねると、サナちゃんはガックリと肩を落として、まるで「鈍感……」とでも言うかのような顔をした。 なによ。同じ学校の人が居たからって、別に関係ないじゃない。全校生徒が300人くらいはいるんだから、そりゃ1人ぐらいはそこに居たって変じゃないでしょ。現に、これまでの下校途中で、同じ中学校の生徒から追い抜かれたり、すれ違ったりしてたんだから。 「ちょっと、何なのよ。ハッキリ言ってくれないと分かんないわよ!」 サナちゃんが何を言いたいのか、本当にサッパリ分からなかった私は、怒ったようにしてそう言うと、彼女は「ふっ」とニヒルな笑みを浮かべて驚くべきことを口にした。 「おんなじ3組になったコだよ」 「はぁ?」 また、何を訳の分からないことを……。 入学式直後に家にも帰らないで、こんな所でのんびり食事なんかしてる女の子なんて、そうそういる訳ないじゃない。しかも、それが同じクラスメートだなんて。 しかし、そんな訳はないとは思いつつも、念の為、私はまた例の女の子を見てみることにした。 今度はしっかり見てやろうじゃない。両眼2・0は伊達じゃないわよ。 私は気合を入れて、目を凝らした。 え~っと……。 その女の子の外見はというと……天然パーマだろうか? 腰までありそうな長い黒髪が、少し波を打っている。あごの輪郭はほっそりとしていて、こうやって遠くから見ただけでも分かるくらい、とても綺麗な女の子のようだった。 何やら一所懸命にテーブルの上で手を動かしているが……。 ああ、眼鏡かな? 眼鏡を拭いてるのね。確かに、眼鏡をかけた女の子は2、3人くらいクラスに居たような気がするけど。 「でしょ?」 頃合を見て、私に同意を求めてきたサナちゃんに対し、私は、 「え~、あんな綺麗な人、同じクラスに居なかったわよ。きっと、2年か3年の先輩だって。すごい落ち着いた雰囲気だし」 と、否定した。 「もうっ、ゼッタイそんなことないってば~」 「そんなことあるわよ」 どうせテストか何かで、上級生も早く授業が終ったんだろう。 「んぐぐ……じゃぁ、確かめてみようよ」 ええっ!? そう言ったサナちゃんは、私が止めるよりも早く、その女の子に向かって大手を振り出してしまった。 「ちょ、ちょっと止めてよ。恥ずかしい」 「大丈夫だって。自信あるんだから」 自信があるとかないとか、そういう問題じゃないでしょうがっ!! |
|
やっぱり四の五の言わずに、タクシー呼んでれば良かったかも……。 まだ学校から自宅までの半分も歩いていないというのに、私は両手に抱える鞄の重さに辟易してしまっていた。 「…………はぁ……」 またしても、思わず溜息が漏れる。 腕や肩などが痺れを切らして、今にも暴走しそうな状態だ。 私は、運動神経は悪い方ではないし、体を動かす事も嫌いではない。が、昔からどういう訳かスタミナが続かないのだ。まぁ、普段の不摂生がたたってるのだろう、とは思うけど。 毎日毎日が格闘だから仕方がない、と言えば格好良く聞こえなくもないが、要は夜遅くまでパソコンの前に座っている自分が悪いのだった。 ちょうど差し当たった交差点の信号が赤になっていたのを機に、それまでどうにか動かしていた足を止めた私は、いったん鞄を地面に降ろした。 本当なら、思いっきり両腕を上に押しやって伸びをしたいところだが、周りの目が気になるので、そんなことは絶対にできない。ただ、小さく肩を回しつつ、いつの間にか曲がっていた背筋をピンと張り直した。 ふぅ、どうしようかな……。 おもむろにブレザーのポケットに手を突っ込むと、ケータイの硬い感触がハッキリと伝わってくる。 呼ぼうと思えば、いつでも呼べるのよね。でも、こんな街なかで10分も20分もボケっと待ってるのも逆に面倒だし……う~~ん。 とりあえず、ここを渡ってしまってから考えるか。 信号が青になったので、ポケットから手を出して鞄を拾うと、左右から来ていた車が止まったのを確認してからゆっくり歩き出した。 っていうか、お腹空いた。今日は朝ご飯、食べてこなかったし……って、それはいつものことか。お母さん、ちゃんとお昼ご飯の準備をしてくれてるのだろうか? あの人、不精だからなぁ。どうせ帰ってから「お弁当買ってきたら?」とか、何食わぬ顔で言われそうな気がする。タクシーより前に、まずは家の方に電話いれといた方が良いような……。 そんなことを考えながら、私は横断歩道を渡り終えた。 ここを右に曲がって20分強程歩くと、やっと自宅に着くって所だ。 だけど私はその方向へは曲がらず、もう少しだけ前進して、すぐ前にある自転車屋の駐車スペースと歩道との境い目まで進んでから、再度鞄を降ろした。 そして、早速、ケータイを取り出す。 そのケータイは、黒に近いグレーの二つ折りタイプのもので、最近流行っているカメラ機能などは付いてない少し型遅れの機種だ。2年前に親に買ってもらってからずっと使い続けていて、バッテリーの持ちが悪くなった気がするが、これより良いデザインの物が出ないので機種変更するつもりは全くない。 どうせかけてくるのは親と兄姉だけで、ほとんどお飾りみたいなもんだし。……あ、いや、あと1人、忘れた頃にいきなり電話してくる人間がいたわ。まぁ、あの人はある意味別格だからどうでもいいんだけど。 片手でそのケータイを開けた私は、自宅の方へとダイヤルして耳元にそえた。 うちは私も含めて5人家族だが、電話に出るのは間違いなくお母さんだろう。お父さんと姉貴はそれぞれ会社と高校だし、兄貴は大学生なので、家を出て学生寮に入ってからもう2年になる。 トゥルル……と3回ほどコールが鳴り、 「はい、時谷です」 案の定、お母さんの声だ。 「あ、お母さん」 「聡美?」 「うん」 「どうかしたの?」 「いや、今学校終って帰ってるところなんだけど、お昼ご飯は何?」 私がそう尋ねると、お母さんは、 「え~~っと……」 と少し考えた後、 「何がいい?」 はぁ、やっぱり準備してなかったか。 いつもの事とはいえ、ガックリと肩が落ちる。 「ご飯は炊けてるの?」 「今から炊こうかなって」 いや、嘘つかなくていいから。何年あんたの娘をやってると思ってるのよ。まったく。 口にはしていないが、「今日はメンドクサーイ」という、明るいながらもダラけた声の調子が、私の気分をさらに萎えさせると同時に、どこか可笑しくて思わず笑ってしまいそうになる。 別にこんな不精な性格だからと言って、母は料理が苦手という訳ではない。それどころか、ひいき目もあるかも知れないが、その味付け加減は抜群だと私は思っている。もちろん家事全般にかけても、母親としての役割は充分に果していた。 「ふぅん、じゃぁお母さんもまだ食べてないの?」 「うん。何か食べたいものでもある?」 「……ん~~、特にはないけど~」 「じゃあ、お弁当か何か、好きなの買ってきたら?」 ほらきた。ちょっと隙を見せたら、すぐこれだから。 自分の子供がお腹を空かせてこれから帰ってくるというのに、市販の弁当で、しかもその子供に買って来させようとするとは……。流石だ。母よ。今日が晴れの入学式だということを忘れてはいないだろうか。 まぁ、言ったところで無意味なので、わざわざ口に出したりはしないが。 ただ、そうは思いつつも、お母さんの気だるいという気持ちは少なからず解かる。やるべき事はきちっとやるが、やらなくて済む事まで力みたくはないものだ。 「ん、分かった。途中でどっか寄ってくね」 私は快諾した。 というか、お母さんの頭の中はもう私が買って帰ることになってるだろうから、いまさら「アレ食べたいから作って」と言うのも可哀想な話である。私が帰宅のついでに、ちょちょっと買い物をするだけでお母さんの気が楽になるのなら、お安い御用だ。 「お金は持ってる?」 「……うん、大丈夫。あ、あと、タクシーで帰りたいんだけど、いい?」 私がこうお母さんに許可を得るのは、もちろん、帰宅後にお弁当代と一緒にタクシー代も請求するからである。 「荷物もいっぱいになるし」 と、とっさに浮んだ、もっともな理由も付け加えた。 ただ、理由を付け加えなかったからといって、「駄目」と言う母ではない。 「はいはい。番号は分かる?」 「大丈夫。ケータイに登録してあるから」 許可は、すんなりと下りた。 多分、私が理由を付け加えなくても、お母さんはほとんど同じ台詞を返してきただろう。そういう母だ。 そして、 「じゃあ、気を付けてね」 ここでようやく母親らしい言葉を……しかし、とてもあっさりした口調で言い、私はそれに、 「分かった」 とだけ応えた。 母はあまり過度な心配をしない。それは、何となくだが、私のことを信用してくれているのだろうと感じられて、私も余計な反抗心を持ったり非行に走ることもなく、お互いに親子としての自然な距離を保つことができた。 さて、事が決まれば話は早い。 後は、お昼ご飯を買ってタクシーを呼んでさっさと家に帰るだけだ。 私の思考回路はもうすでに、自らのお腹と献立の協議に入り始めていた……が。 そういえば、 「あっ、お母さん」 電話を切りそうになっていた母を、急いで呼び止める。 「ん? 何?」 何? じゃないわよ。あんたのお昼ご飯はどうすんのよ! 私は、喉まで出かかったツッコミをグッと堪えて、 「お母さんは何食べるの?」 と尋ねた。 「ああ、お母さんは何でもいいわよ。家にある物で。ご飯は冷凍してるのがあるし、漬物もたしか残ってたから」 「そ、そう……」 …………。 なんだか肩をすかされた気分。 まぁ、いつもこんな感じだから驚きはしないが、この無頓着ぶりには、少なからず呆れてしまう。 別に、お母さんは荷物の多い私に気を使ってくれているとか、家計のことを気にして余分な買い物をしないとか、そういう訳ではない。何度も言うが、こういう母なのだ。その証拠に、 「あ、待って。お母さんはアレでいいわよ」 「アレって?」 「いつもの」 もしや、 「いつものって、いつもの……アレ?」 「ポテトとシェイク」 ほらほら、きたきた! 私に気を使うどころか、よりによってそう来たか。 なんとも人使いの荒いお人だこと……。 「はぁ」 私は小さく溜息を吐いた。 と、それが、電話ごしにお母さんの耳に届いていたのか、 「お店が遠いならいいわよ。無理して寄らなくても」 一応、私に気を使って言ってくれてるらしい。 が、できれば食べたいわぁ、という思いがその声色に表れているうえに、いつもお母さんにはそれなりに苦労をかけてるせいもあり、私は断ることができなかった。 「はいはい、買っていくわよ」 それに……。 私は自宅とは正反対の方向に顔を向けた。 「それに、お店は今ちょうどすぐそこだから」 運が良いのか悪いのか、お母さんお気に入りのバニラシェイクを売ってるお店は、ほんの100mもない距離に建っていた。 「そお? じゃあ、お願いね」 「はいはい」 そしてこの瞬間、あれこれ悩む以前に、私のお昼ご飯も決まってしまったのだった。 |